
 われら六稜人【第3回】伝統を守る…2人の選択
われら六稜人【第3回】伝統を守る…2人の選択
 西尾清司氏(77期)の選択
西尾清司氏(77期)の選択庄屋の屋敷を遺す
-
いつからあの家の保存運動にのめり込んでしまったのだろう…。父が亡くなり相続問題が生じました。遺産の大半をあの家が占めていました。ちょうどバブルが崩壊し、地価がどんどん下落している頃でした。あんな大きな屋敷を維持管理していくことは、かなり負担が大きく、また、個人の住居としても大変使いづらいものであることは明らかです。そこで一度は物納を決心して、その手続きをとりました。屋敷を後世に残すことができない…先祖に申しわけない、という気持ちで一杯でした。
物納するには建物を解体しなければなりません。そこで、せめてもの「おわかれ」の記念に…と、建築に携わる知人に鑑てもらったのです。そして彼の報告書を見て驚きました。自分の家の価値をあまり認識していなかったのです。離れが武田五一博士の設計だとか、屋敷が完存していて且つほとんど改築されていないとか…いろいろな指摘を受けました。結局、文化的な視点から見てかなり価値の高いものである…ということに気がついたのです。
 また、「屋敷が解体されるかも知れない」という噂を聞きつけた近所の人たちが署名運動を展開してくださいました。現在すでに4万人以上の署名が集まっています。そんなふうに、あの家の保存活動に対する支援者が集まるなか…ちょうど時を同じくして、28歳という若さで夭折した天才音楽家、貴志康一の生涯に取材した創作オペラが、近所のメイシアターで上演されまして…たまたま「貴志の生家だ」というので、この屋敷でも関連のちょっとした音楽会が企画されたんです。「あぁ、こういう使い方があるんだな…」と再認識しましてね。
また、「屋敷が解体されるかも知れない」という噂を聞きつけた近所の人たちが署名運動を展開してくださいました。現在すでに4万人以上の署名が集まっています。そんなふうに、あの家の保存活動に対する支援者が集まるなか…ちょうど時を同じくして、28歳という若さで夭折した天才音楽家、貴志康一の生涯に取材した創作オペラが、近所のメイシアターで上演されまして…たまたま「貴志の生家だ」というので、この屋敷でも関連のちょっとした音楽会が企画されたんです。「あぁ、こういう使い方があるんだな…」と再認識しましてね。
建物は使ってこそ価値があると思います。それで、当初は「保存会」だったのですが、屋敷の定期的な公開のほかに、茶会、華展、能や地唄舞の会、コンサート等さまざまな文化活動の会場として、また建築を専攻する学生さんの研究対象としても利用されるようになり…「保存活用会」へと発展してきたのです。
非常にたくさんの方々の賛同を得た結果、吹田市という地域の枠を越える広がりをもった組織が、ボランティアを中心としながら生まれてきたのです。中心になって活動いただいているメンバーの方には頭の下がる思いです。
一方「文化財保護は行政の考えること」という人もいて、吹田市に保存の打診をしてみました。埋蔵文化財の対応に手一杯の吹田市からは「茶室だけ」とか「離れだけ」とか、部分的な保存を考えてはどうかという案が出たようです。それらを移築して敷地の一箇所にまとめてしまえば…というのが彼等の案でした。
 私は…単に建築物を保存したいわけではありません。建物単体ではなくて、庄屋屋敷という「有形のもの」を残すことで、地域のコミュニティや時代の風習、文化という「無形のもの」を残し、後世に伝えていきたい…。「庄屋屋敷」の住まい方やあり方を残したいと願っているのです。
私は…単に建築物を保存したいわけではありません。建物単体ではなくて、庄屋屋敷という「有形のもの」を残すことで、地域のコミュニティや時代の風習、文化という「無形のもの」を残し、後世に伝えていきたい…。「庄屋屋敷」の住まい方やあり方を残したいと願っているのです。
屋敷構え全体の保存…主家、離れ、茶室、露地、庭園、土蔵…これらの組み合わせで初めて、各々の建物の役割とかハーモニーが伝えられると思うのです。しかも、それらが活用され、いわば「動態保存」されることを目指したいのです。
「保存運動をしたら税金を納めんで済むのですか?」
「いったいナンボの得になりますねん?」
そんなコトをよく訊ねられます。お金の面で割り切っていたら、もうとっくの昔に更地になっています。いま私たちのやっていることは、経済面から見たら大変バカげた営為だと思います。
そもそも、今の日本の「公共物と私有財産」に関する制度は大きな矛盾をはらんでいると思います。私は土地とか建物といったものは一種の「公共物」だと思います。しかし見事なまでに、日本の街の景観はバラバラです。「民間の私有財産」ということで土地の所有者が勝手に出来るわけです。世界的にも、日本ほどバラバラの街並みは珍しいと思いますよ。まるで「統一感」というものに美を感じていないかのようで。
共有財産(わたしたちのもの)に対するモラルも俄然低い。たとえば、バス停なら平気で吸い殻をポイ捨てしてしまいます。自分の庭に吸い殻を捨てる人が…いるでしょうか。すべてが、私有財産(わたしのもの)を基準にした…「おかね」というものさしで計る習慣が、果たして日本人を幸せにするのでしょうか…いまそのツケが来ていると思うンですね。
 どんどんと新しいものに生まれ変わるのが世の中ですが、将来の展望をしっかりと立てて、後世に残すべきもの、伝えていくべきものと、そうではないものとをしっかり峻別することが必要なのではないでしょうか? そういう時期に来ていると思うンです。
どんどんと新しいものに生まれ変わるのが世の中ですが、将来の展望をしっかりと立てて、後世に残すべきもの、伝えていくべきものと、そうではないものとをしっかり峻別することが必要なのではないでしょうか? そういう時期に来ていると思うンです。
やはり、土地は社会から借りうけているものであって、個人の所有物としての意味あいは薄いものではないかと思います。しかし現実には、今の日本人は土地にしがみついて生きています。
いったい「文化財」って何なのでしょうか。私は…土地にくっついて景観を形作る伝統的な建築物が「歴史的景観=文化財」だと思っています。個性的で、何か心象風景を伝えていくもの…。そうした思いで、吹田の屋敷の保存活用を考えています。どうか、そのような家が存在することを知っていただき、まずは実際に見ていただいて、活用の輪を広げ、話題にしていただければ嬉しい限りです。

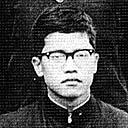 六稜の伝統も…
六稜の伝統も…
同じような「心の」無形財産と思います。
 旧庄屋屋敷保存活用会のサイトへ
旧庄屋屋敷保存活用会のサイトへ
Update : Nov.23,1997