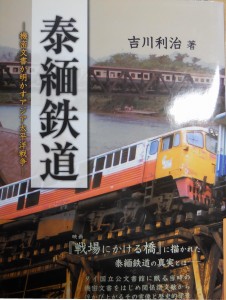お久し振りです。2018年にミャンマーについて11回投稿させて頂き、しばらく休憩の後、2020年3月に再開した途端に コロナでミャンマーへの旅行が殆ど不可能となり、4月10日に「一日も早く新型コロナ騒ぎが落ち着いて、再び投稿再開できる日が遠くないことを祈っております」と申したまま、現在(2022年4月)に至ってしまいました。ご存知の方々も多いでしょうが、ミャンマーの場合は、昨年2月1日に国軍によるクーデターが起こり、その後民衆による抗議デモが続く中で遂に国軍側が発砲して多くの死傷者が発生して、現在に至っても対立(戦闘やテロ行為を含む)が続いています。国軍側は、来年の8月に総選挙を行って政権移譲すると明言しているのですが、抵抗勢力側がそれをボイコット、或いは積極的に妨害することも予想されます。つまり、仮にコロナ感染が収束しても、少なくとも来年夏までは政治的混乱が継続する見込みで、日本から普通に観光旅行に行けるような状態になるのは、更にその先でしょう。本当に残念です。
お久し振りです。2018年にミャンマーについて11回投稿させて頂き、しばらく休憩の後、2020年3月に再開した途端に コロナでミャンマーへの旅行が殆ど不可能となり、4月10日に「一日も早く新型コロナ騒ぎが落ち着いて、再び投稿再開できる日が遠くないことを祈っております」と申したまま、現在(2022年4月)に至ってしまいました。ご存知の方々も多いでしょうが、ミャンマーの場合は、昨年2月1日に国軍によるクーデターが起こり、その後民衆による抗議デモが続く中で遂に国軍側が発砲して多くの死傷者が発生して、現在に至っても対立(戦闘やテロ行為を含む)が続いています。国軍側は、来年の8月に総選挙を行って政権移譲すると明言しているのですが、抵抗勢力側がそれをボイコット、或いは積極的に妨害することも予想されます。つまり、仮にコロナ感染が収束しても、少なくとも来年夏までは政治的混乱が継続する見込みで、日本から普通に観光旅行に行けるような状態になるのは、更にその先でしょう。本当に残念です。
実は、2年も投稿が途絶えていたこともあり、今年の1月に、六稜同窓会のかたから継続の意思につきお問い合わせを受けました。ミャンマーとの強い縁が出来て36年、こよなくミャンマー及び国民の人達を愛する私は、何とか来年末までには皆さんにミャンマー旅行をお薦めできる日が来ることを信じて、取り敢えず(大変失礼ですが)まずは繋ぎの投稿をさせて頂きたい、と御返事した次第です。
そして、暫く、どのようなことを申し上げようかと考えていたところに、御高承のウクライナ侵攻が始まりました。ミャンマーの悲劇とウクライナを重ね合わせて考える方達も多いのですが、もちろん性質は大きく異なります。ミャンマーの場合、実際に戦闘やテロ行為が行われているとはいえ、あくまで一つの国家の中での権力闘争なのですから、話し合いの努力を行うべきです。ところが、ウクライナでさえロシアと停戦交渉の努力を続けているというのに、ミャンマーでは、抵抗勢力側も国軍側も相手を全面的に否定し、決して話し合おうとしません。それどころか、もし、欧米や日本での公の席で国軍と抵抗勢力側の話し合いの必要性を主張すると、在外ミャンマー人のみならず、マスコミや多くのミャンマー関連の研究者の方々からの非難轟々となる、いわゆる「炎上」する状況が続いています。
もちろん、国軍側には正当性は一切ありません。昨年のクーデターは余りにも愚かでした。国軍の発砲で家族の命を失った人達を含め、抵抗勢力側が、国軍との一切の話し合いを拒否する気持ちは重々良く判ります。しかし、例は悪いかもしれませんが、自分の子供を誘拐した犯人から身代金要求の電話があった時に、「お前がやっていることは極悪犯罪だ。身代金は一切払わない。今すぐ人質を解放しろ!」と叫んで電話を切る親がいるでしょうか?人質をとって立て籠っている銀行強盗に対して、もし警察が「悪いのはお前だ!今すぐ武器を捨てて出てこい!」と繰り返すだけで、強盗側の要求には一切耳を貸さないとしたら、家族が人質になっている人はそれを支持できるでしょうか?私は、以前の投稿で申した通りミャンマーとの歴史的友好関係を維持してきた日本の政府こそ、両者の話し合いを実現するために積極的に動いて貰いたい、と心から願っています。
久し振りの投稿なのに、随分と暗い話になってしまいましたが、今ミャンマーについて語るとすれば仕方ないでしょうね。もう一日も早い平和を祈るばかりです。
なお、日本の一部のマスコミの報道だけを読んで、まるでミャンマー全土で戦闘やテロ行為が行われているかのように誤解される方々もおられるかも知れませんが、決してそうではありません。国境周辺等、もともと1948年の独立後、少数民族武装勢力と国軍との戦闘が続いてきた地域は今でも同様なのですが、少なくとも都市部での治安はクーデター以前と同様のレベルで保たれています。現地の日系企業の殆どは、クーデター以前とほぼ変わりなく活動を続けています。在留邦人は、コロナ以前の約5千人から、今は約1千人に減少していますが、これはコロナさえ収束すれば、次第に回復していくでしょう。もちろん例外はあり、例えば、国軍系企業との合弁でトップシェアでビールを生産してきた日本の某ビール会社は、撤退を決めましたが、私はその決断はやむを得ないと思いますが、詳細は控えておきます。私個人としては、そのビールのあっさりした味が大好きで、その会社の協力無しで国軍系企業があの美味しいビールを生産し続けられるとは思えず、とても残念ですが。
それでは、現地の事情が大きく好転するか、そうでなければ今年の年末くらいを目途に、改めて投稿させて頂きたいと思います。
最後になりましたが、上の写真は、北部マンダレー近郊の「ピンウールウィン」という避暑地の植物園で育った、桜の木です。戦時中に日本人が植えたものと推察されます。今回の話題に相応しい写真が見当たらず、間に合わせのようで恐縮ですが、またこれを観に行きたいです。